住宅用防災機器の設置の義務付けについて
平成18年6月1日から有田川町火災予防条例第29条の2の規定により、新築住宅に住宅用防災機器(以下「住宅用火災警報器」とします)の設置が必要になります。
既存住宅は平成23年6月1日から適用されます。
消防法第9条の2に基づいて改正された有田川町火災予防条例が、平成18年6月1日に施行されたことに伴い、住宅等に「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられました。(第29条の2) なお、設置する場所は下記のとおりです。
1. 就寝の用に供する居室(条例第29条の3第1項第1号)
2. 1.が存する階の階段(1.が避難階の場合を除く。)(同条同項第2号)
3. 1.が存する階から2階下の階の階段(1.の1階下の階の階段に住宅用防災警報器等が設置されている場合を除く。)(同条同項第3号)
4. 1.が存する階(避難階に限る。)から2以上うえにある階に居室がある場合のその最上階の階段(同条同項第4号)
5. 1.から4.までに該当しない階で7平方メートル以上の居室が5以上をある階の廊下(廊下が存しない場合は階段)(同条同項第5号)
- 住宅用火災警報器には、「単独型」と「連動型」がありますのでお選びください。
- 日本消防検定協会の「NSマーク」のついた商品を選びましょう。
なぜ住宅用火災警報器が必要なのですか
住宅火災から大切なご家族を守るために住宅用火災警報器は大切な役割を果たしています。
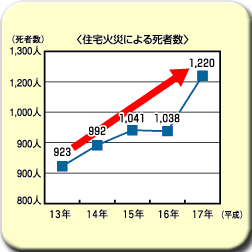
住宅火災による死者は増加中

死者の約6割が65歳以上の高齢者
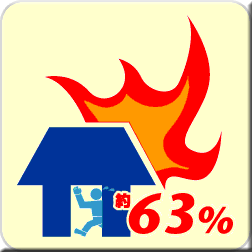
死亡原因の約6割が逃げ遅れ

建物火災の死者は、住宅火災による死者が約9割に上ります。
どの部屋に取り付けるの
有田川町の条例で定められた設置基準です。
赤に白抜きの場所は取付けが義務付けられています。
青に白抜きの場所は取付けをおすすめするところです。

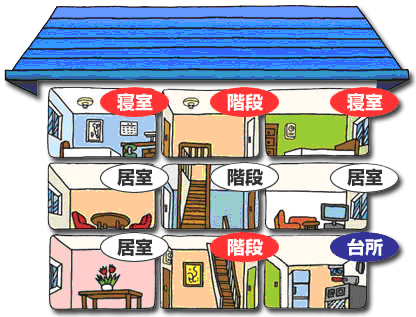
7平方メートル(四畳半)以上の居室が5以上ある階には、廊下に火災警報器の設置が必要です。
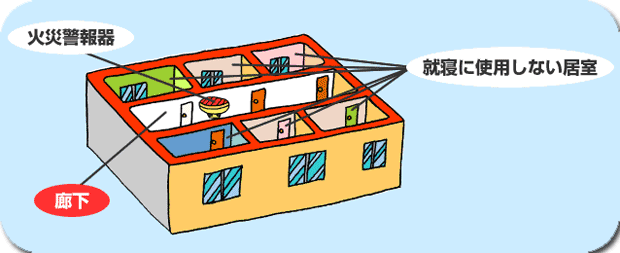
どの位置に取り付けましょう
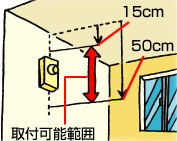
壁取付けの場合
天井から15~50センチ以内に住宅用火災警報器が来るようにします。
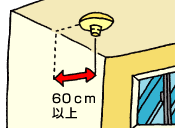
天井取付けの場合
住宅用火災警報器の中心を壁から60センチ以上離します。
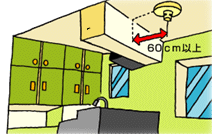
はりなどがある場合は
住宅用火災警報器の中心をはりから60センチ以上離します。
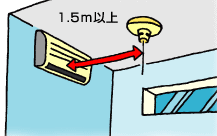
エアコンなどの吹き出し口付近の取り付けは
換気扇やエアコンなどの吹き出し口から1.5メートル以上離します。
どんな種類があるの
- 住宅用火災警報器の種類
煙式(光電式) 寝室・階段・台所など煙が火災警報器に入ると音や音声でお知らせします。

火災 ガス漏れ複合型
住宅用火災警報器とガス漏れ警報器の機能を複合した警報器
(注意)これらの火災警報器には、電池を使うものや家庭用電源(AC100V)を使うものがあります。
- 補助装置
高齢者の方、目や耳の不自由な方には、音や光の出る補助警報装置の増設をおすすめします。

注意事項
- 乾電池タイプの住宅用火災警報器は、電池の交換が必要です。電池切れの警報が出た場合に、交換する必要があります。
- 住宅用火災警報器の交換期限がきたら交換してください。 (自動試験機能が付加されている機器を除きます。)購入時に「取扱い説明書」「点検方法」など確認してください。
- 自動火災報知設備又はスプリンクラー設備が設置されている場合は、火災警報器の設置の必要はありません。
悪質業者に注意!
高齢者の方や一人暮らしの方を狙った訪問販売や電話による勧誘から「住宅用火災警報器」の購入を迫られることが予想されますので、特に注意が必要です。
無条件解約(クーリング・オフ)の対象になります。
- ご不明な点は下記までお問い合わせください
有田川町消防本部予防課 52-7199
吉備金屋署予防指導係 52-5950
清水消防署予防指導係 25-1243
このページに関するお問い合わせ
消防本部(予防課)
〒643-0811 和歌山県有田郡有田川町大字庄1042
電話番号:0737-52-7199
ファクス:0737-52-5952
メールフォームによるお問い合わせ
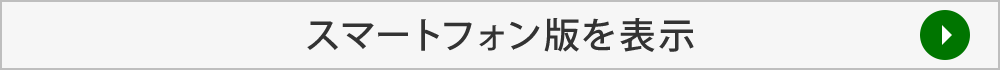





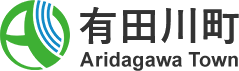






更新日:2019年03月15日