予防接種
予防接種には法律で接種が義務付けられている「定期の予防接種」と保護者の方が接種するかどうかを決める「任意の予防接種」があります。
定期の予防接種
- 接種料は無料です。(一部個人負担あり)
- それぞれの年齢に合わせて個別に通知します。
| 内容 | 予防できる疾病 | 標準的な接種期間 |
|---|---|---|
| BCG | 結核 | 生後5ヶ月から8ヶ月の間に1回 |
| B型肝炎 | B型肝炎 |
生後2ヶ月から9ヶ月の間に3回 |
| 五種混合 | ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib | 1期初回:生後2ヶ月から12ヶ月の間に3回 1期追加:初回接種終了後半年~1年半の間に1回 |
|
四種混合 |
ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ | 1期初回:生後2ヶ月から12ヶ月の間に3回 1期追加:初回接種終了後1年~1年半の間に1回 |
| 二種混合 | ジフテリア・百日せき | 11歳から12歳の間に1回 |
| ポリオ | ポリオ | 初回:生後2ヶ月から12か月の間に3回 追加:初回接種終了後1年~1年半の間に1回 |
| 麻しん・風しん混合 | 麻しん・風しん | 1期:1歳から2歳になるまでの間に1回 2期:保育所年長に該当する年度内に1回 |
| 日本脳炎 | 日本脳炎 | 1期初回:3歳から4歳の間に2回 1期追加:初回接種終了後1年後に1回 2期:9歳から10歳の間に1回 |
| 子宮頸がん ワクチン |
ヒトパピローマウイルス |
13歳となる日の属する年度初日から当該年度末日までの間 2月以上の間隔をおいて2回目、3月以上あけて3回目 9価ワクチンは、15歳になるまでの間に1回目の接種を行えば、2回で接種完了が可能。(ただし、1回目と2回目の間隔が5月未満の場合は、3回目の接種が必要。) |
| ヒブワクチン | インフルエンザb型 | 初回:生後2ヶ月から7ヶ月の間に3回 追加:初回接種終了後7ヶ月から13ヶ月までの間隔をおいて1回 |
| 小児用肺炎球菌ワクチン | 肺炎球菌に起因する肺炎 | 初回:生後2ヶ月から7ヶ月の間に3回 追加:生後12ヶ月から15ヶ月の間に1回 |
| 水痘 | 水痘(水ぼうそう) | 1回目:生後12ヶ月から15ヶ月まで 2回目:1回目終了後6ヶ月から12ヶ月間隔をおく |
| ロタウイルス | ロタウイルス |
ロタリックス:生後2ヶ月から24週までの間に2回 |
| 高齢者の インフルエンザ |
インフルエンザ | 65歳以上の方、60歳以上65歳未満で一定の障害のある方で、年度毎に1回 接種時期は10月から翌年の1月までの間 一部自己負担金が必要 |
|
高齢者 |
肺炎球菌に起因する肺炎 |
65歳の者、60歳以上65歳未満で一定の障害のある方、(これまでに23価肺炎球菌ワクチンを1回以上接種した者は、対象外となります) |
- 五種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、Hib感染症)は、令和6年4月1日から導入されました。
- 子宮頸がんワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンは、平成25年4月1日から定期の予防接種に指定されました。
- 水痘、高齢者肺炎球菌ワクチンは、平成26年10月1日から定期の予防接種に指定されました。
- ロタウイルスワクチンは、令和2年10月1日から定期の予防接種に指定されました。
- 子宮頸がんワクチン(9価)が令和5年4月1日から公費対象となりました。
任意の予防接種
- 接種料は全額自己負担で医療機関によって異なります。
- 保護者の方が接種するかどうかを決めるものですので役場から案内はしません。
- 接種を希望される方は直接ご希望の医療機関にお問い合わせください。
| 内容 | 予防できる疾病 | 標準的な接種期間 |
|---|---|---|
| 季節性 インフルエンザ |
インフルエンザ | 13歳未満は2回。13歳以上は1回または2回 |
| おたふくかぜ | おたふくかぜ | 1歳以上で1回 |
| A型肝炎 | A型肝炎 | 1歳以上で初回2回。初回接種後24週経過後に追加1回 |
| 帯状疱疹 |
帯状疱疹 |
50歳以上 不活性化ワクチン (2回接種) 乾燥弱毒生ワクチン(1回接種) |
| 黄熱 | 黄熱 | 9ヶ月以上で1回 |
| 狂犬病 | 狂犬病 | 全年齢3回~6回 |
小児インフルエンザ予防接種費用を助成します!
対象者
有田川町の住民基本台帳に記載されている人で令和7年1月31日までに生後1歳以上であり、令和6年度末に16歳未満(中学生以下)の子ども
助成回数・額
令和6年度末に13歳未満の子ども(小学生以下)の場合、1人に対し2回まで、令和6年度末に13歳以上16歳未満の子ども(中学生)の場合、1人に対し1回までとし、1回あたり3,700円の接種費用が上限となります。
接種費用が上限を下回る場合は、その額が助成額になります。
令和6年10月1日から令和7年1月31日までの接種分が助成の対象になります。
令和7年度から帯状疱疹ワクチンの制度が変わります。
注意:国の方針により、帯状疱疹ワクチンは令和7年4月から定期接種になりました。
現時点で国から示されている制度は以下のとおりです。
帯状疱疹の定期予防接種について(国の方針)
〇定期接種の開始時期 :令和7年4月1日
〇定期接種対象者 :過去に帯状疱疹ワクチンを接種していない、以下のいずれかに該当する人(過去に帯状疱疹ワクチンを接種した人は、定期接種の対象外です)
1.当該年度に65歳になる人
2.60歳以上65歳未満の人で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害で日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人(免疫機能の障害を有する人(免疫機能の障害で障害者手帳1級相当)
3.当該年度に70・75・80・85・90・95・100歳になる人(令和7年度から令和11年度までの5年間の経過措置)
4.100歳以上の人(令和7年度のみ)
〇ワクチン :乾燥弱毒性生水痘ワクチン(1回皮下接種)又は
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(2回筋肉内接種)のいずれかを選択
〇自己負担金 :あり
乾燥弱毒性生水痘ワクチン 1回 2500円 自己負担
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン1回 6000円(合計 12000円) 自己負担
〇その他
帯状疱疹ワクチンの交互接種(2種類の異なるワクチンを組み合わせて接種すること)は出来ません。
注意:国より令和7年4月1日より帯状疱疹ワクチンを定期接種とする方針が示されました。なお、現在有田川町で実施しております、帯状疱疹予防接種(任意接種)費用助成事業は、令和7年3月末で終了になりました。
予防接種について、詳しいことは「和歌山県情報館」で確認できます。
4種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)予防接種が完了していない方へ
令和6年4月より5種混合ワクチンの予防接種が開始されたため、4種混合ワクチンの販売中止が決定しました。
4種混合ワクチンの在庫がある間のみ接種できます。
合計4回の接種が完了していない人は、速やかに接種するようにしましょう。
(注意)5種混合ワクチンは、従来の4種混合ワクチン(百日せき、ジフテリア、破傷風、ポリオの4種類)にヒブワクチンを加えた混合ワクチンです。
すでに4種混合ワクチンとヒブワクチンで接種を開始している方が、5種混合ワクチンへ切り替えをする場合は、ヒブワクチンと4種混合ワクチンの残りの接種回数が、揃っている必要があります。
・4種混合ワクチンとヒブワクチン接種の残りの回数が同じ場合は残りの接種回数分を5種混合ワクチンに代えて接種できます。
・4種混合ワクチンの接種は未完了、ヒブワクチンの接種は完了している場合は、4種混合ワクチンの残りの回数分を4種混合ワクチンの在庫で完了させる必要があり、原則5種混合ワクチンに代えて接種することは出来ません。
3回目の接種終了後、6か月後(標準的には1年から1年半後)に追加接種ができますので、速やかに接種するようにしましょう。
(注意)対象者: 生後2か月から生後90か月
日本脳炎予防接種を受けましょう
日本脳炎の予防接種後におもい病気になった事例があったことをきっかけに、平成17年度から平成21年度まで、日本脳炎の予防接種のご案内を行いませんでした(いわゆる「積極的勧奨の差し控え」)。
その後、新たなワクチンが開発され、現在は日本脳炎の予防接種を通常通り受けられるようになっています。
そのため、平成7年4月2日生まれ~平成19年4月1日生まれの方は、20歳未満の間、いつでも日本脳炎の定期予防接種を受けることが平成23年5月20日からできるようになりました。 母子手帳で接種歴を確認し、不足している場合は接種を受けて日本脳炎から身を守りましょう。
接種をご希望の方は、金屋庁舎健康推進課・清水行政局住民福祉室まで手続きにお越しください。
日本脳炎について、詳しいことは「厚生労働省ホームページ」で紹介されています。
このページに関するお問い合わせ
健康推進課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
電話番号:0737-22-4503(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-3644
メールフォームによるお問い合わせ
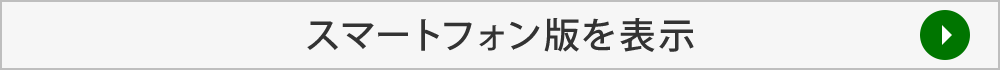





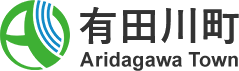






更新日:2025年03月31日