国民健康保険税
国民健康保険に加入したら被保険者となり、保険税を納付していただきます。
保険税は世帯単位で計算され、世帯主が納税義務者になります。
保険税は国保の医療分、後期高齢者医療支援金分、介護納付金分をそれぞれ算出し、その合計を保険税として納めます。
介護分については、国保加入者のうち40歳以上65歳未満の人に加算されます。
医療分・支援金分・介護分の保険税は、次の3項目の計で算出しています。
- 所得割額:加入者全員の前年の所得金額に、税率を乗じて計算します。
- 均等割額:加入者の人数に、一人当たりにかかる額を乗じて計算します。
- 平等割額:一世帯当たりにかかる額を加算します。
(資産割額は令和6年度より廃止されました。)
令和7年度 有田川町国民健康保険税の税率
令和7年度国民健康保険税の税率は以下の通りです。
| 所得割率 | 8.00% |
|---|---|
| 均等割額(一人あたり額) | 31,800円 |
| 平等割額(一世帯あたり額) | 22,200円 |
| 医療分の課税限度額 | 660,000円 |
| 所得割率 | 2.8% |
|---|---|
| 均等割額(一人あたり額) | 10,200円 |
| 平等割額(一世帯あたり額) | 7,000円 |
| 支援金分の課税限度額 | 260,000円 |
| 所得割率 | 2.4% |
|---|---|
| 均等割額(一人あたり額) | 10,100円 |
| 平等割額(一世帯あたり額) | 5,200円 |
| 介護分の課税限度額 | 170,000円 |
令和5年度分、令和6年度分の国民健康保険税の税率 (PDFファイル: 428.5KB)
倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険税の軽減措置(非自発的失業軽減)
雇用保険の受給資格をお持ちの方で、倒産・解雇等により職を失った方(特定受給資格者)や、 正当な理由のある自己都合により離職した方(特定理由離職者)について、国民健康保険税の 負担を軽減します。
軽減を受けるには申請が必要となります。
次の条件を全て満たす方が対象となります
- 平成29年4月1日以降に失業された方
- 失業日時点で65歳未満の方
- 失業給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記に該当する方
| 離職理由コード | 離職の理由 |
|---|---|
| 11 | 解雇 |
| 12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
| 21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
| 22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
| 31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
| 32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
| 離職理由コード | 離職の理由 |
|---|---|
| 23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
| 33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
| 34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
軽減額の金額とその期間
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得を100分の30(7割減)とみなして行い、法定軽減についても同様にみなした所得で判定されます。 軽減の期間は、離職の翌日から翌年度末までの期間で、最大2年間となります。
軽減を受ける手続き
離職により国民健康保険に加入した方で、離職理由コードが上記に該当する場合は、吉備庁舎税務課・金屋庁舎やすらぎ福祉課・清水行政局住民福祉室の窓口にて、軽減申請書をご提出ください。
その際、雇用保険受給資格者証 をご持参ください。
国民健康保険税の軽減措置
国民健康保険税は、被保険者の前年中の所得等に応じて計算し課税されますが、前年中の世帯の総所得金額が一定基準以下の場合には、国民健康保険税の 均等割額・平等割額 を減額し、負担を軽くする軽減制度があります。 軽減制度の適用に申請は必要ありませんが、世帯主及び加入者全員の申告が必要となります。
(ただし、給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている場合や、税法上の被扶養者、19歳未満の方などは除く)
| 軽減割合
|
令和7年度分の基準額 (世帯主・国保被保険者・特定同一世帯所属者の所得の合計金額で比較) |
|---|---|
| 7割軽減 | 世帯の所得の合計額が「43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下となる場合 |
| 5割軽減 | 世帯の所得の合計額が「43万円+(30万5000円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下となる場合 |
| 2割軽減 |
世帯の所得の合計額が「43万円+(56万×(被保険者数+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下となる場合 |
注釈:特定同一世帯所属者とは、年齢到達等により後期高齢者医療の適用となり国保資格を喪失した方で、国保喪失後も継続して同一の世帯に所属する方をいいます。(同一の世帯に所属する方とは、国保喪失以後も世帯主が変わっていない状態を言います)
未就学児にかかる均等割額の減額
令和4年度から、未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)にかかる均等割額の5割が減額となります。。この法定軽減の適用を受けている世帯は、軽減後(7・5・2割軽減)の額から5割減額となります制度の適用に申請は必要ありません。
| 法定軽減 | 均等割額 | 減額適用後 |
|---|---|---|
| 一般世帯(軽減なし) | 42,000円 | 21,000円 |
| 2割軽減世帯 | 33,600円 | 16,800円 |
| 5割軽減世帯 | 21,000円 | 10,500円 |
| 7割軽減世帯 | 12,600円 | 6,300円 |
産前産後にかかる均等割額・所得割額の減免
令和6年1月から、産前産後期間の国民健康保険税を減免する制度が開始されました。
・対象
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方
(注釈)妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
・免除方法・対象期間
出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月までの4ヶ月相当分の保険税が免除されます。
(注釈)多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が免除されます。
・受付期間
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
・届出に必要な書類
1.減免申請書2.母子健康手帳など
国民健康保険税の納付期限
国民健康保険税を、納付書および口座振替(普通徴収という)により一括納付いただく場合の納期限は7月末となり、期別により納付いただく場合は、8回に分けた金額で7月から2月までの毎月月末が納期限となります。
また年金からの天引き(特別徴収という)となっている方は、事前にお知らせする金額を、年金の支給月に天引きさせていただいています。
|
年金支給日に保険税を天引きし、翌月10日までに納付されます。 |
| 1期分 | 7月末 |
|---|---|
| 2期分 | 8月末 |
| 3期分 | 9月末 |
| 4期分 | 10月末 |
| 5期分 | 11月末 |
| 6期分 | 12月末 |
| 7期分 | 1月末 |
| 8期分 | 2月末 |
| 隋時期 | 3月以降の月末 |
注釈:月末が土日・祝日の場合は、翌営業日が納期限です。
また、年度途中から国保に加入された方は、届け出いただいた月の翌月から納期が始まり、加入月数に応じた保険税額を残りの納期の回数で割って納めていただきます。
例:8月末で社会保険を脱退し、9月に国民健康保険加入の届け出を提出した方の場合。
4期分(10月末納期)から納付が始まり、9月~3月の7か月分の保険税額を、4期~8期の5回に分けて納めていただきます。
国民健康保険税 年金からの天引き(特別徴収)
国民健康保険税を口座振替や納付書により納付いただいている方につきましても、下記の要件全てに該当する年金受給者の方々につきましは、原則として年金から天引きする「特別徴収」という方法に変更となります。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者であること。
- 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳~74歳であること。
- 世帯主の年金受給額が年額18万円以上であること。
- 国民健康保険税と世帯主の介護保険料を合わせた特別徴収額が、年金受給額の2分の1を超えないこと。
複数の年金を受給されている場合は、年金保険者(社会保険庁や国公共済組合など)の種別で定めた優先順位により1つの年金を選択し、特別徴収できるかの判断を行います。 年金からの天引き予定となる方については、事前にお知らせをいたします。その後の資格異動などにより、年金天引きが中止となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
国民健康保険税 年金特別徴収と口座振替の選択制
年金からの天引きとなる方について、それまでの保険税が滞納となっていない場合に限り、口座振替に変更することが出来ます。(納付書によるお支払いは選択できません。)
口座振替に変更を希望される場合は、申請書の提出が必要となります。
それまで、年金天引きを継続されていた方についても変更することが出来ますので、詳しい内容につきましては、税務課までお問い合わせください。
お手続き
「国保税 納付方法変更申請書」の提出(役場窓口にてお渡しします) その際、口座振替依頼書のお客様控えをお持ちください。
注釈:これまで、口座振替をされたことがない方については、事前に各金融機関窓口にて口座振替依頼書の提出が必要です。
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4
電話番号:0737-22-3272(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7821
メールフォームによるお問い合わせ
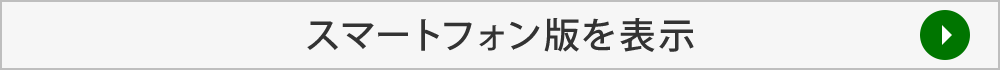





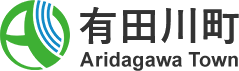






更新日:2024年04月01日