イントロダクション
和歌山県有田川町は、紀伊半島の北西部に位置する豊かな自然と歴史のある町です。有田川町東部には、奇観の棚田として知られている蘭島(あらぎ島)があります。平成25年10月17日、あらぎ島と周囲の景観が「蘭島及び三田・清水の農山村景観」として国の重要文化的景観に選定されました。全国で36番目、和歌山県内では初めての選定です。「蘭島及び三田・清水の農山村景観」は、大部分を山間地が占める厳しい自然条件下にあって、有田川上流域に展開する独特の地形をいかした農林業や紙漉きなど、これまでの人々の活動によって形成された独自性の高い文化的景観です。
蘭島(あらぎ島)

明暦元年(1655)山保田組(現在の有田川町清水地区に相当する地域)の初代大庄屋であった笠松左太夫によって開発された新田。有田川に沿って弧状をなす扇形とも表現される棚田は、全国的にも価値の高い景観です。
| 全体面積 | 約2.8ヘクタール |
|---|---|
| 水田面積 | 約2.4ヘクタール |
| 水田枚数 | 54枚 |
| 水田平均面積 | 約4アール |
| 棚田の平均勾配 | 1/12 |
| 耕作者 | 6軒(平成8年 あらぎ島景観保全保存会を結成) |
| 主な栽培米の品種 | ミネアサヒ、ヤマヒカリ、もち米 |
| 平成8(1996) | 第4回「美しい日本のむら景観コンテスト」農林水産大臣賞受賞 |
|---|---|
| 平成11(1999) | 「日本の棚田百選」に選定される |
あらぎ島の地名の由来
あらぎ島は地元では単に「島」と呼ばれています。古くから川沿いの耕地を「島」と呼ぶことがあり、蘭島はまさに「島」と呼ぶにふさわしい場所です。「蘭」については、江戸時代の文化7年(1810)に著された『山保田続風土記』という書物の中に、「蘭」に「アララギ」とふりがなが振られており、「蘭」は本来「アララギ」と呼ばれていたと考えられます。「蘭」の解釈については、主に次の3つの説がありますが、定説はありません。
- 「アララギ」とは「イチイ」の別称であることから、イチイの木を指すとする説
- 「アララギ」とは「ノビル」の古名であることから、もとは野草のノビルが群生していたと考える説
- 新しく開墾した土地として、全国に地名が残る「あらき」から転じたと考える説
笠松左太夫(かさまつさたゆう) ?~寛文13年(1673)
有田郡山保田組(現在の有田川町清水地区)の初代大庄屋を務め、私財を投じて数多くの用水路の整備やあらぎ島を始めとした新田開発、和紙生産を興すなど組内の基盤整備と改革に心血を注いだ郷土の偉人です。弁天山(有田川町久野原)では、人夫や農民に削った岩の粉一升と米一升を交換し、岩盤に水路を通す難工事を完成させたという逸話が伝えられています。地元では「左太夫さん」と呼ばれ、人々に親しまれています。
文化的景観とは
文化的景観とは、手つかずの大自然ではなく、人間が生きていくために自然に働きかけた結果、長い年月をかけて形作られてきた風景のことであり、「人と自然の共同作品」とも呼ばれています。日本各地には、特色ある文化的景観が数多く存在しますが、それらは先人達のたゆまぬ努力によって現在に継承されてきた、かけがえのない文化遺産であるとともに、地域の「個性」を雄弁に物語るものでもあります。
文化的景観は、魅力ある風景を次世代へ継承していく取り組みとして、平成16年の文化財保護法の一部改正により新たな文化財の種類として誕生し、特に重要なものについては「重要文化的景観」として保護する制度が整えられました。
文化的景観の詳細については、以下のwebサイトをご覧ください。
蘭島及び三田清水の農山村景観の概要
| 選定の名称 | 蘭島及び三田清水の農山村景観 |
|---|---|
| 選定日 | 平成25年10月17日 |
| 面積 | 110.7ヘクタール |
| 重要な構成要素 | 蘭島、水田、上湯用水路、建造物、有田川、湯川川、水力発電施設など |

選定区域
今回重要文化的景観に選定された区域は、蘭島に用水する上湯用水路によって水田が営まれている範囲と、笠松左太夫によって紙漉きの村として開拓され、歴史的に関わりの深い小峠地区、歴史ある眺望地であり、緩斜面を利用した棚田の景観が広がる三田区の一部を含めた110.7ヘクタールの範囲です。





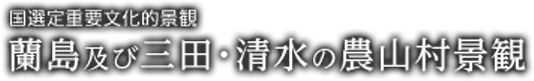

更新日:2019年03月19日